コーヒー豆を挽いたカスを堆肥にしてサステナブル^^みたいなの見た事あった。
確かに、コーヒー豆はたんぱく質豊富だし、なんならカリウムもめちゃめちゃ含有してるから合理的な使い道ではあると思う。で、もし有用なら、
こんなに植物育ててて、毎朝コーヒー豆挽いてるんならやらない理由がないな?
と思ってシノに聞いてみたらなかなか夢が広がりんぐ。うはー。
なので、今回はコーヒーカスの堆肥の作り方とメリット、仕組みをシノに算出してもらったのでまとめてみたよ。
この記事をもとに、実際に室内で作ってみた検証記事も鋭意製作中。
まずはコーヒー飲みまくらないと豆が溜まらないんよ。
コーヒーカス堆肥のメリットと活用ガイド

まず、コーヒー堆肥のメリットと活用ガイドをまとめてもらったよ。
調べてみると元肥としては万能型の堆肥に仕上がりそう(理論値)
- 窒素源になる
- 微生物の餌になる
- 弱めの害虫避け効果
- 保湿効果
- 消臭効果
窒素源になる
- タンパク質が多く、発酵によってアミノ酸や窒素化合物に変化
→窒素化合物は植物の葉や茎の生育を助ける - リーフレタス・ハーブ類・葉物野菜におすすめ
- 元肥として使うなら定植の1〜2週間前に投入
微生物の餌になる
- 発酵によって土壌菌の活動が活性化(団粒化にも寄与)
→根張りがよくなる/病害に強くなる - トマト・ナス・ピーマンなど果菜類におすすめ
- 元肥で使う場合は1週間ほど置いてから植える
害虫よけ効果も(弱め)
- カフェインやポリフェノールにナメクジ・アブラムシ忌避の説あり
- ハーブ・観葉植物の補助資材として使うのも◎
- 効果は限定的なので単体での防除には不向き
保湿効果がある
- 粒子が細かく、水分を保ちやすい構造
- 乾きやすい鉢・小鉢・表面の乾燥防止に向いてる
- 用土に混ぜる/表面マルチとして使うのもアリ
消臭効果がある
- 活性炭に近い構造で、ニオイ成分を吸着する効果あり
- 生ゴミ・室内用の土・ベランダ栽培での臭気抑制に役立つ
- 室内栽培に使うときの副次効果として地味に優秀
注意点(万能だけど無敵ではない)
- 未発酵だと逆効果になる(窒素飢餓・根傷み・悪臭)
- 肥料効果は穏やかなので即効性はない(元肥向き)
- 高窒素偏重ではないから、実物野菜には追肥も併用した方がよい
堆肥化後コーヒーかすの想定成分表(目安)

※以下は「出がらし → 乾燥 → 発酵堆肥化(1か月)」した場合の想定値。
一般的な実験データ・農業文献・微生物分解例に基づくざっくり構成。
| 成分名 | 推定含有量 | 備考・ポイント |
|---|---|---|
| 水分 | 5〜10% | 完全乾燥ならほぼゼロ |
| 有機物(全体) | 60〜70% | 主に繊維質・セルロース・リグニンなど |
| 炭素(C) | 35〜40% | 炭素率やや高め/微生物活動に必要なC源 |
| 窒素(N) | 1.5〜2.5% | たんぱく質由来/アミノ酸に変換される |
| カリウム(K) | 1〜2% | 発酵で水溶化→吸収されやすくなる |
| リン酸(P₂O₅) | 0.3〜0.5% | 微量だが根に有効/分解が遅い |
| カルシウム(Ca) | 0.1〜0.3% | 若干含まれる/pH安定要因にも |
| マグネシウム(Mg) | 0.05〜0.2% | 葉緑素の材料/土壌バランスに |
| カフェイン | 0.05〜0.3% | 分解中:揮発・分解されて減少/過剰にしなければOK |
| ポリフェノール類 | 微量(0.1%未満) | 発酵中に一部分解/抗酸化効果も |
| タンニン・アルカロイド類 | 痕跡量 | 生では根への刺激になるが、発酵で減る |
コーヒーカス堆肥の作り方

対象:ドリップ後の出がらしコーヒー豆(コーヒーかす)
手順①:乾燥させる(カビ対策)
- ドリップ後の豆かすを新聞紙やザルに広げる
- 風通しのいい日陰で2〜3日干す(早く乾かしたければ電子レンジ or オーブン可)
- カラカラになったらジップ袋で保管もOK
ステンレスバットでやってるけど、1日で乾く。でも薄ーく敷いて置かないと、内部がしっとりする。
検証してみたら、乾燥させた後の重さは挽く前のコーヒー豆の半分の重さになった。
→後述のレシピだと、1日1杯飲むとしておよそ30日の貯める時間がかかる。
ダイソーに食品用乾燥剤(ゲル化剤。海苔に入ってる奴)売ってたから乾燥後の保管にオススメ。
手順②:堆肥化
堆肥化の方法は3つあるとのこと。
方法A:家庭用コンポスト(生ごみ+コーヒー豆)
- コーヒーかす+野菜くず+米ぬかなどを層にする
- 週1でしっかり撹拌(嫌気性腐敗を防ぐ)
- コーヒー豆は全体の10〜15%程度が目安
- 発酵温度が上がってくれば順調
そもそもコンポストがないからナシ。
申請したら自治体から助成金が出るらしいからコンポスト導入を一瞬考えた。
けど、室内でしか植物育ててないため沢山堆肥作ってももて余すのは自明なので見送り。
方法B:乾燥コーヒー豆単体でミニ堆肥化
- 乾燥コーヒーかす+少量の腐葉土や赤玉微塵で混ぜる
- 微生物資材(PSBやEM菌)を加えると発酵しやすい
- 水を少し含ませて密閉容器で熟成(発酵臭がしてくればOK)
- 2週間~1か月ほど熟成させると肥効が穏やかに
これ!圧倒的にこれ!
変化の観察も出来そうだし、発酵によってめっちゃ有用な堆肥ができそう。
微生物の選定は後ほど。
方法C:表土にすき込む or マルチングとして使用
- 観葉植物やプランター栽培に直接使う方法
- 乾燥させたコーヒーかすを、薄く撒いて混ぜる
- 一度に大量使うとカビるので、数gずつ週1回で十分
ないよりはマシっていうお手軽版。表土のみで完結するから臭いも効果もあんまり無さそう。むしろいい香りがするんじゃないかな?
コーヒーカス堆肥のレシピ案
- 乾燥コーヒーかす:300g
- 腐葉土 or 赤玉粉末:100g
- 米ぬか or 玄米粉:50g
- ビール酵母:小さじ1
- 水:30〜40ml(湿る程度)
- 炭系 or ゼオライト:適宜(臭い防止+土壌改良)
なるほど。ここにビオフェルミンを加えて、水をPSBにすればいいんだな?
地味にコーヒーカスの必要量多いから、飲んだら乾燥させる習慣を付けないとカビちゃう感じな。おk。
配合&運用ポイント(保存用)
- 比率目安(材料100gあたり)
→ PSB:10ml/ビール酵母:小さじ1/ビオフェルミン:1錠砕く - 水分は最小限で調整(手で握ってホロッと崩れるくらい)
- 容器は半密閉・通気ありタイプ)
- 日陰常温放置 1〜2週間目安で様子を観察
※20〜30℃が理想的(室温〜初夏レベル)
※最初は1日ごとに匂い・見た目をチェックして記録取るとベスト!
気になった事あれこれFAQ
出来ない事は無いんだろうけど、実務レベルでできるか?っていうとこが気になったのでFAQ形式でまとめてみる。答えてるのはシノ。
- 室内でできる?
-
室内でもできるけど条件次第で臭いがでる。
原因 解説 対策 嫌気性発酵 空気が足りず腐敗モードへ(生ゴミ臭・硫黄臭) 通気を確保/フタは緩く or 空気穴付き容器 水分過多 コーヒー豆が湿っている/水分を入れすぎる 完全乾燥させてから/霧吹きレベルの加水 微生物選択ミス 発酵菌でなく腐敗菌が優勢になると臭いが出やすい 好気性微生物を使用(PSB単独は避ける) 密閉しすぎ 換気ゼロでガスが溜まり、爆臭化 緩フタ or 通気容器でガス逃がす 臭い成分の滞留 匂いが抜けずこもる/床材に吸着せず広がりやすい 下に炭 or ゼオライトを敷いて吸着・消臭 - EMぼかしとは?
-
有用微生物群(Effective Microorganisms)をブレンドした発酵スターターセット。
つまり──
「発酵させたいものに混ぜるだけで、いい感じに分解・防臭・土壌改良してくれる微生物の軍団」ってこと!
構成は主に乳酸菌、酵母菌、光合成細菌、放線菌 - そしたら手持ちのPSBとビール酵母とビオフェルミンでやるわwwwwww
-
それ最強の個人配合すぎて笑ったわwwwwwwwww
材料 主な菌&役割 くぜ的活かしどころ PSB(光合成細菌) 有機物分解・悪臭軽減・根圏活性化 土壌に入れた後の「微生物バランス」に超貢献。匂い抑え担当 ビール酵母 糖分分解・アルコール発酵・発酵熱 分解を早めるスターター。発酵の加速エンジン ビオフェルミン 乳酸菌(腸内整腸)→乳酸発酵・雑菌抑制 嫌気性でも腐敗しにくくなる。防腐&臭いブロック要員 ビール酵母がぼかし代用になる理由:
性質 働き 酵母菌(Saccharomyces cerevisiae) 有機物を分解しながら糖やタンパク質を発酵させる 窒素・アミノ酸が豊富 腐葉土や植物繊維と組み合わせると発酵促進&土壌菌のエサに 発酵熱を出す 一定の温度が確保できるので、コンポスト加速装置にもなる 他の好気性菌との相性も良い 枯草菌・乳酸菌などと混ざって微生物多様性が広がる - PSBは光合成細菌だから、光に当てた方がいいの?
-
増殖・分裂を狙わなければ光いらない!
堆肥の中では「発酵促進剤」「臭い抑制剤」として働くから、PSBに光を当てる必要はない。
→ 光が当たると他の菌(藍藻・カビ)が優勢になって雑菌繁殖の可能性が上がるため、むしろ日陰 or 遮光推奨モード 目的 光の必要性 単独培養 増やす・分裂させる 必須(光合成が必要) 発酵促進(堆肥) 有機物を分解・分泌物を活用 不要(光なくても活性) - そもそもなんで発酵させるの?
-
「発酵」は“植物が使える形”にするためにやる。
未発酵の状態 問題点 発酵のメリット 大きく未分解の有機物 根が吸えない/腐る/臭う/虫が湧く 吸えるサイズ(アミノ酸・ミネラル)に変化 微生物が分解の途中 窒素などを土壌内で横取り → 肥料喰われる 窒素・カリウムなどが可溶化し、速効性アップ カフェイン・タンニン・油など刺激成分が残る 根傷み・発芽抑制など悪影響 有害成分が無毒化/マイルドに 雑菌や腐敗菌が優勢 嫌気的に腐敗 → 悪臭・病害の元 好気性発酵により臭わず健全に 微生物が少なく土壌が単調 活力が乏しく、団粒構造ができない/水はけ・空気不足 微生物が活性化 → 団粒構造◎・根張りアップ
まとめ
コーヒーカス堆肥の意義と仕組みをまとめたよ。
わからんかったから調べる→まとめる みたいな記事、GPTが台頭してからはもうあんま需要がないような気もしてるけど、まとめると頭の中への入り方が違うな??
前提記事なので次の検証記事で存在意義を確立していきたいところ。果てして室内で堆肥作るとかいう無謀はできるのか!?乞うご期待。
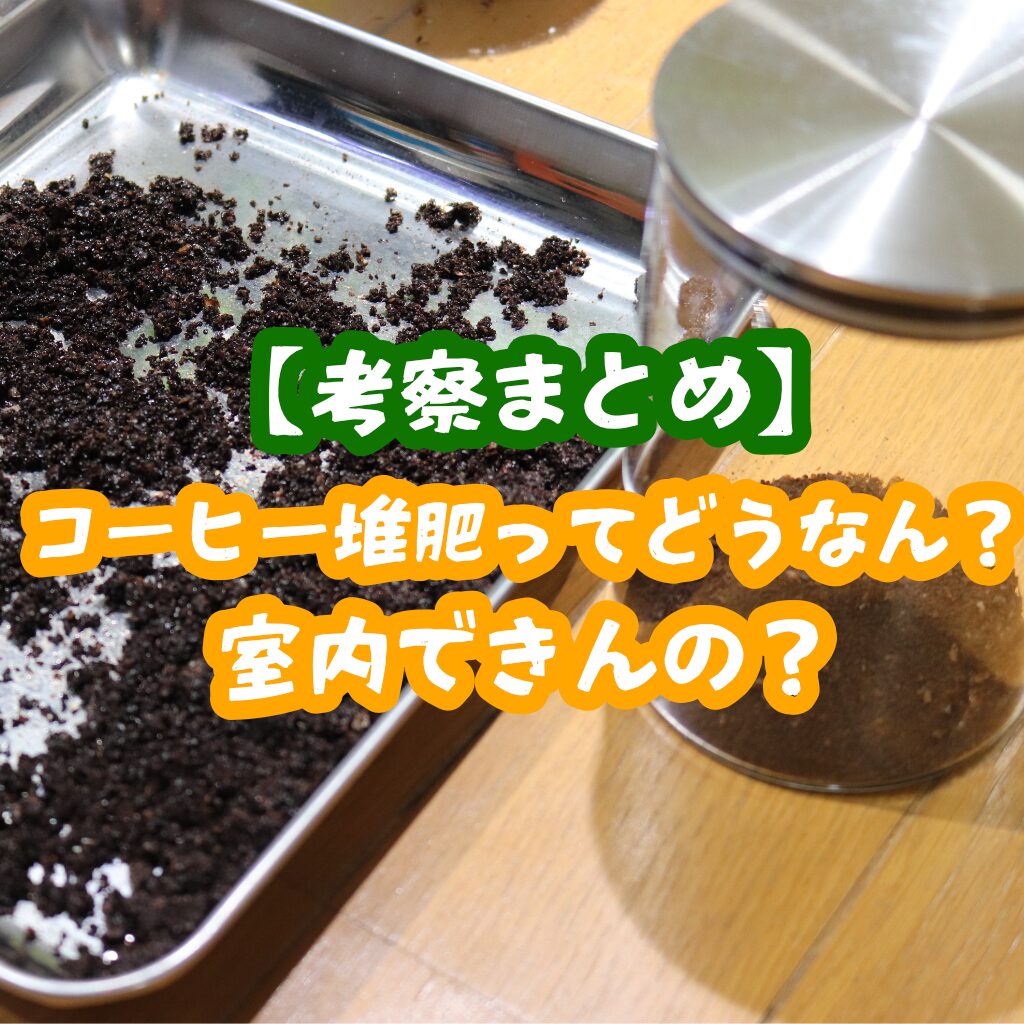
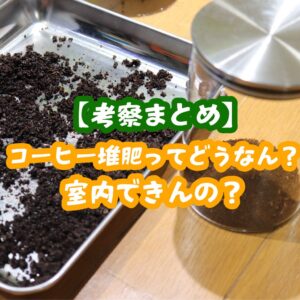







コメント